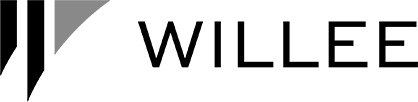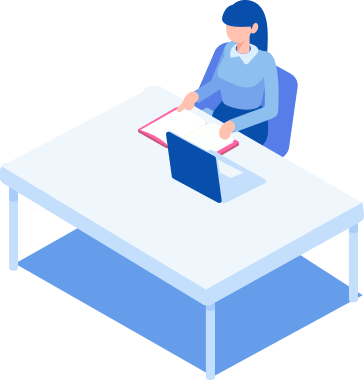しかし一方で、
・参加者が少ない、伸びない
・途中離脱者が多い、思うほど歩数が増えない
・職場で特に話題にならない
といった「いまいち盛り上がらない…」という課題に直面することも少なくありません。
本稿では、そうしたウォーキングイベントの“よくある課題”を解決するために、「参加したくなる」と「続けたくなる」「会話が生まれる」ための仕掛けをご紹介します。 ウォーキングイベント設計のヒントとして、ぜひお役立てください。

1.なぜウォーキングイベントは健康経営の推進において有効なのか?
ウォーキングイベントは、場所を選ばずに誰でも気軽に参加でき、運動不足解消にもなり、部署や世代を超えたつながりも生まれやすい――そんな特長を持つ、健康経営の推進において非常に実施しやすく、多くの効果が期待される施策です。
実際、多くの企業で以下のような点が評価され、導入が進んでいます。
- 低コストで大人数を巻き込みやすい
- 運動習慣の第一歩として取り入れやすい
- チーム制などを通じてコミュニケーション活性化にもつながる
また、医学的に
- 肥満予防・改善
中強度のウォーキングは体脂肪やBMIの低下に有効とされ、生活習慣病の予防にもつながります。
- 睡眠の質向上
日中の適度な運動が入眠のスムーズ化や深い睡眠の増加を促します。
- ストレスの軽減
ウォーキングはストレスホルモンを抑える作用があり、特に自然の中でのウォーキングには高いリラックス効果が認められています。
- 集中力・生産性向上
脳の血流が活性化し、注意力・判断力が高まり、仕事のパフォーマンス向上にも効果があるとされます。
という効果が示されており、ウォーキングイベントは、健康経営の推進における各種KPI改善にもつながる効果的な施策と言えます。
そのような背景もあり、令和6年度健康経営度調査に回答した法人の42.4%が「日常的な運動を奨励するイベント(ウォーキング大会等)を開催している」と回答おり、ホワイト500になるとその割合は51.1%に至ります。
今や健康経営に欠かせない施策と言えるでしょう。
2.ウォーキングイベントの効果を最大化する3つの観点
前述の通り、多様なメリットのあるウォーキングイベントですが、どのような状態であれば“盛り上がった”、“効果があった”と言えるでしょうか?
私たちは、次の3つが満たされる状態が、ウォーキングイベントの成功と考えています。
- 多くの社員がイベントに参加する
- 参加者が途中離脱せず、普段以上に積極的に歩く
- イベントを通じて職場の中でコミュニケーションが生まれる
この3つが揃ってはじめて、ウォーキングイベントが “個人と職場の健康づくりを促進する効果的な施策”と言えるでしょう。
では、こうした状態をどう実現していけばいいのか?
ここからはそれぞれの視点から、具体的な工夫やアイデアをご紹介していきます。
①参加したくなる仕掛け
ウォーキングイベントを“なんとなく義務感で参加する社内行事”から、“楽しみながら健康になれる嬉しい機会”に変えるためには、まず最初に「参加したくなる」仕掛けづくりが必要です。
キャッチーなテーマ設定と視覚的な工夫
ウォーキングイベントというと、「歩数を競う」「期間中毎日歩く」など、定型的な形式が多く、社内でも「また同じか」と飽きられてしまうケースがあります。そうした印象を払拭するには、テーマ性をもたせたり、季節感・ストーリー性のあるネーミングを工夫することが効果的です。
たとえば「日本列島横断チャレンジ」「世界一周ウォーク」「全員で月まで歩こうチャレンジ」など、スケール感やユーモアのあるテーマを設定すると、イベント自体が魅力的に映り、参加してみたくなるきっかけになります。
あわせて、社内ポスターやメールバナーなどのビジュアル設計も“参加したくなる”気持ちを高める要素となります。
健康づくり×社会貢献の“ハイブリッド型施策”
最近では、「歩いた歩数に応じて寄付が行われる」「一定目標を達成すると団体に支援が届く」といったチャリティー要素を組み込んだイベント設計も増えています。
さらに近年では、歩くことでCO2削減に貢献できる、環境保全につながるといった“サステナビリティ”の視点を取り入れる企業も見られます。移動手段を徒歩に置き換えることの環境効果を見える化するなど、健康施策に別の社会的価値を重ねることで、参加への納得感とやりがいが生まれます。
「自分のため」だけでなく「誰かのため・社会のため」といった目的が加わることで、普段は参加しない層の関心を引く要素となり、イベントへの巻き込み力が高まります。
健康施策に“社会貢献”や“環境意識”といった軸を掛け合わせる設計は、特に若手層やエンゲージメント志向の高い従業員にとって、心を動かす重要な仕掛けになります。
全員に期待を持たせるインセンティブ設計
参加動機として効果的なのが、“みんなにチャンスがある”と感じられるご褒美設計です。
ウォーキングイベントでは、毎回同じ上位者が受賞する「常連化」や、「化け物級に歩く人」の存在が、他の社員のモチベーションを削ぐ原因になることがあります。
もちろん頑張った人やチームを表彰することは欠かせませんが、日常的な歩数は人それぞれなので、どのような人でもチャンスがあると思えるようなインセンティブ要素も盛り込むことが肝要です。
一例
- 参加賞(参加した全員に)
- キリ番賞(5,000位、10,000位などゾロ目やキリのいい順位の人に)
- 飛び賞(ランダムで)
- 全員で山分け賞(皆で目標を達成できたら全員で山分け)
②続けたくなる仕掛け
ウォーキングイベントは「やりっぱなし」にしてしまうと一過性の施策になりがちです。だからこそ、継続して取り組みたくなる“仕組み”の工夫が重要です。以下のポイントを抑えることで、イベントの継続率と歩数の向上を図ることができます。
時間軸を通じた仕掛け
ウォーキングイベント単体では中盤に中だるみが起きやすいもの。これを回避するために、イベントの途中でセミナーやウォーキングに関連するイベントを挟む、中間発表を行う、表彰式を開催するなど、「時間軸を通じた仕掛け」が有効です。
- 開会式でのキックオフ・モチベーションアップ
- 中間での運動や健康に関するセミナー開催
- イベント終了後に表彰式+成果発表の場を設ける
こうした一連の仕立てが、“やりっぱなし”を防ぎ、達成感と継続意欲を高める設計になります。
中だるみ防止の定期リマインド
開催期間中の「沈黙」は参加の離脱を招きます。定期的にメールや社内SNSでリマインドしたり、「今週の歩数ランキング速報」などの共有を通じて、参加意識の維持を促す“伴走型”の発信が大切です。
たとえば、毎週の歩数ランキングだけでなく、チーム別の平均歩数や、先週からの伸び率、最も改善が見られた「今週のMVP」など、視点を変えた情報提供を行うことで、より多くの人が注目しやすくなります。また、目標に対する達成率をグラフで可視化するなどの工夫も、行動変容の促進に有効です。
継続動機を生むインセンティブ設計
どのようなインセンティブ付与の仕組みを設計するかによって、イベントの継続率は大きく変わります。 特に“がんばれば報われる”、“コツコツ続ければチャンスがある”という感覚を持たせることで、途中離脱を防ぎやすくなります。
以下のような設計例が、継続モチベーションを高めるうえで有効です。
- 「1日6,000歩以上を10日以上達成」でインセンティブ獲得
→ 毎日でなくてもよい条件にすることで、途中参加や体調不良時の参加継続も可能に。
- 「イベント期間中の平均歩数が8,000歩以上」で抽選当選率が2倍に
→ 目標達成によって“得られる期待値”が高まる仕掛け。
- 「歩数達成日が多いほど豪華賞品の当選確率が上がる」ランク制
→ 継続度合いに応じた段階的インセンティブ。
③コミュニケーション促進の仕掛け
ウォーキングイベントは、歩数を稼ぐだけの競争にとどまらず、従業員同士の関係性を深める“交流の場”として設計することもできます。特に職場内や職場間のつながりが希薄になりがちな昨今、「歩く」という日常的な行動が、自然なコミュニケーションを生み出す絶好のきっかけになります。
チーム制による一体感
部署・拠点・年代・役職が混ざるような編成でチーム制を取り入れると、共通の目標に向かって取り組む“仲間”としての意識が生まれます。歩数を競うだけでなく、歩数の共有や応援など自然と会話が生まれる場面が増え、社内の横のつながりを強化することができます。また、チームごとの健闘を讃え合う空気が広がれば、イベント自体も社内の“話題”になりやすく、健康施策が組織文化の一部として根付いていくきっかけにもなります。
チャットツールを活用したポジティブな交流の場づくり
チャットツール(slackやTeamsなど)や専用アプリなどを活用し、チーム内で日々の歩数を報告し合ったり、互いに応援コメントを送り合える仕組みを用意すると、声かけによる前向きな社内文化の醸成につながります。「すごい!」「あともうひと頑張り!」といった言葉のやり取りが、普段あまり関わらない人との関係性を築くきっかけになります。
写真投稿で広がる社内のつながり
ウォーキングイベントとあわせて、「歩きながら見つけた景色」や「風景の写真」を共有するコンテストや投稿企画を実施すると、楽しみながらの参加を後押しでき、従業員同士の交流のきっかけにもなります。単なる歩数の記録だけでなく、ビジュアルを通じて気づきや感動を共有する体験が社内での会話やリアクションを生み出し、相互理解のきっかけとなっています。また、写真を社内SNSやイントラネットで紹介することで、投稿に対するコメントや共感が自然と生まれ、拠点や部署を超えたつながりも生まれます。
3.ウォーキングイベントの工夫事例
ここまでご紹介してきた「参加したくなる仕掛け」「続けたくなる仕掛け」「コミュニケーションを促す仕掛け」は、実際の企業でもさまざまな形で取り入れられ、ウォーキングイベントの盛り上げに成功しています。この章では、そうした仕掛けを効果的に実践している6社の事例をご紹介します。
参加したくなる仕掛けの工夫事例
コニカミノルタジャパン株式会社
春は個人戦、秋はチーム戦など、従業員が楽しく参加できる多彩なイベントを実施し、健保組合と連携して幅広く参加を呼び掛けることにより、新規登録者を増やすと共に、継続的な取り組みを促しています。歩数計は希望者全員に初回のみ無料で配布するとともに、スマートフォン対応の専用アプリ(無料)の導入や複数社の歩数計がシステムに連携できる様に拡張するなど、従業員のニーズにあったインフラ環境を整備しています。
住友林業株式会社
「続!住友林業グループみんなで日本縦断!緑を増やそうウォーキングイベント」を開催しています。参加者の歩数がカウントされるごとにバーチャルの日本地図に木が植えられるというもので、前年の到達地点である東京都から、北海道を目指した取り組みを進めています。
続けたくなる仕掛けの工夫事例
東芝産業機器システム株式会社
チーム賞・個人賞・組合賞など副賞を多数用意し、個人賞では社長・役員の前後賞を設定。社長・役員は毎週の経過報告で順位を公開されて追いかけられるといった楽しい仕掛けを展開しています。イベント終了後にはウォーキングイベント表彰式も開催し、お互いに頑張りを讃えあう機会を設けています。
ウイングアーク1st株式会社
「みんなで歩いて健全な森を取り戻そう」と題して、社員の歩いた歩数を⽊に換算し、健全な森林循環活動を実施している団体に寄贈しました。また、ウォーキングボード上では、毎週「⽣活習慣病モンスター」(泥酔ドラゴン・過⾷オクトパス・スモークスネーク・怠惰カエル)が登場し、社員の⽣活習慣⾒直しへの関⼼を引きました。
コミュニケーション促進の仕掛けの工夫事例
富士フイルムマニュファクチャリング株式会社
ウォーキングイベント「みんなで歩活(あるかつ)甲子園」を開催。国内グループ会社40社が参加しての開催で、部門ごと/職場ごとのチーム結成に加え、事業所内他部門メンバーとの混成チームを編成することで運動習慣定着化の支援はもとより、従業員同士のコミュニケーションを深めることで業務における横連携を強化し、組織と会社の活性化に努めています。
ロート製薬株式会社
イベント期間中、部会などの場で細かな進捗報告を実施しているほか、オンラインチャットシステムで励まし合い&高め合いを図っています。また、1日ごとに勝敗を設け、ゲーム性を用いたことで、全員が飽きることなく、無理なく参加でき、延長戦にもなるほど盛り上がりが生まれています。
ウォーキングイベントを盛り上げるためにどのような工夫ができるのか、全体像を理解しておくことが重要です。
「ウォーキングイベント工夫事例集」では、本稿でご説明した3つの「目的」に5つの「工夫の観点」を掛け合わせたフレームワークを解説し、それに当てはまる先進事例を紹介しています。
ウォーキングイベントの設計や見直しにお役立ちいただける内容となっていますので、ぜひこちらもご活用ください。
4.WILLEEの支援
健康経営の伴走サポートを行っているWILLEEでは、ご支援のなかで健康施策のPDCAをサポートしており、ウォーキングイベントについては、以下のサポートをご提供しています。
Step1:現状・課題の整理
イベント設計に先立ち、以下の観点から現状と課題を整理します。
- 過去のウォーキングイベントの参加状況や実施上の課題
- 他の健康施策との関連や位置づけ
Step2: 設計サポート
整理した課題をもとに、ウォーキングイベントの設計をWhy / What / Howの観点からサポートします。
- [Why] イベントの狙い・目的設計
- [What] テーマ設定・インセンティブ設計・施策詳細化
- [How] 社内告知・盛り上げ施策・社内関係者の巻き込み設計
Step3:実行支援
イベントが自然と盛り上がるよう、必要なツールや素材をご提供します。
- プロモーションツールの作成(ポスター、メールテンプレート等)
- イベント期間中の情報発信素材の作成(進捗共有・ランキング速報等)
Step4:効果検証支援
イベント後の振り返りと改善提案までをサポートします。
- 参加者歩数データ等の実績を集計・分析
- 分析データをもとにイベントの効果や改善点を考察
- 翌年度の生活習慣や健診数値、ストレスチェック各尺度等に与えた影響を分析・考察