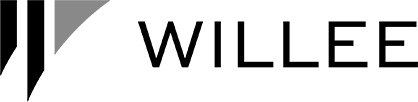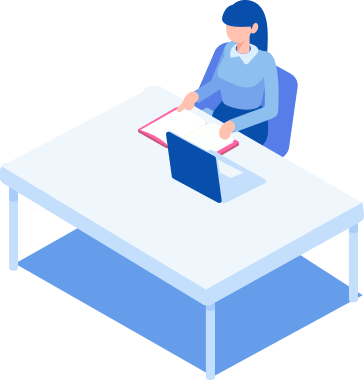こうした課題を解決する手段の一つとして、最近注目されているのが「健康月間」です。 一定期間に施策を集中的に展開することで、参加者の関心を高めやすく、全社的な盛り上がりも生まれやすくなります。
本稿では、健康月間の導入意義を説明し、より多くの従業員が関心を持ち、参加したくなるような仕掛け──“音楽フェス”のような仕掛けづくりの視点から成功のポイントを解説します。
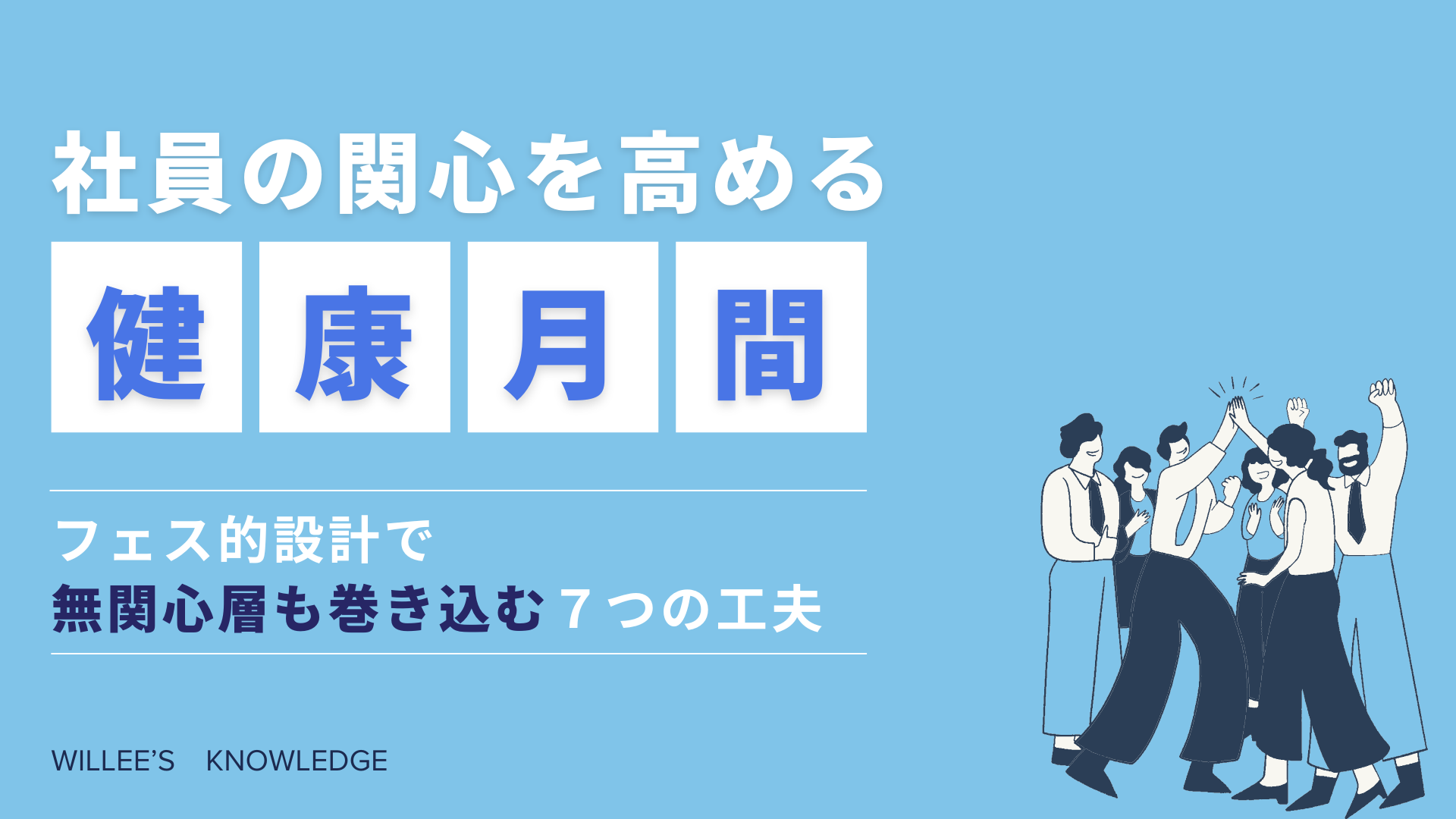
1.なぜ健康施策は“届かない”のか?──3つのよくあるつまずき
健康経営の取り組みを進めている企業ほど、次のような課題にぶつかることがあります。
- 普段の健康施策が“空気”になってしまう
→毎年形式的に実施されているだけで社員の記憶に残らず、社内で話題にもならない
- 実施しても“特定層にしか届かない”
→健康意識が高い層だけが毎回参加し、参加する社員が固定化されてしまう
- 色々取り組んでいるのに、施策がバラバラで印象に残らない”
→ 運動、食事、メンタルなど施策を個別展開しているため、全体像が伝わっていない
こうした“つまずき”を乗り越えるヒントとして、注目されているのが「健康月間」の取り組みです。 健康月間とは、一定期間に健康施策を集中的に展開することで、社員の関心を高め、全社的な盛り上がりをつくりやすくする方法です。
この背景には、厚生労働省と中央労働災害防止協会が10月1日~7日を「全国労働衛生週間」、健康保険組合連合会が10月を「健康強調月間」として推進していることがあります。こうした国全体の取り組みに呼応して、企業でも10月を中心に健康月間を取り入れ、全社的な健康意識の向上を目指す動きが広がっています。
そして、健康月間の効果を最大化するためには、「音楽フェス」のような仕掛けの設計が大きなヒントになります。
なぜ“音楽フェス”なのか。 それは、音楽フェスが「好きなアーティストがいる」「雰囲気が楽しい」「なんとなく楽しそう」など、 人それぞれの興味関心の“入り口”を用意しているからです。
一方、健康施策はどうしても「健康に関心のある人」しか参加しにくい傾向があります。 だからこそ、多様なニーズに応え、空気感も含めて“健康に関心のない人でも参加したくなる設計”が重要なのです。
ポイントを押さえて設計していくことで、健康施策への関心が薄かった層にも“楽しみながら触れる”体験を提供し、組織全体として健康意識の底上げを図ることができるでしょう。
2.健康月間を成功させる7つの設計ポイント
音楽フェスが様々な参加動機を引き出す仕掛けで人を惹きつけるように、健康月間も多様な興味関心を捉えながら盛り上げていく必要があります。
ここでは、WILLEEがご支援の中で培ってきた知見をもとに、健康月間の成功に向けた7つのポイントをご紹介します。
[1] 関心を引き付けるコンセプト設計
例えば「身体と脳の状態を知る」「疲れから解放する」「コンディションを整える」など、従業員に刺さるテーマがあると、健康月間の意義が伝わり、参加のモチベーションにつながります。(キャッチコピーは別途必要)
[2] 多様なニーズに応える施策構成
「身体を動かしたい」「睡眠を改善したい」「自分の状態を知りたい」など関心の入口は人それぞれ。複数の施策を用意することで、幅広い社員ニーズに応えることができます。
[3] 話題性を生む目玉施策の設計
タレント講師の登壇や役員との特別トークなど、注目を集めやすい施策を設けると社内で話題になりやすくなります。
[4] 巻き込みを促す参加型施策設計
拠点対抗イベント、健康川柳の募集、体力測定会など、社員同士の関わりが生まれる企画で“みんなでやる感”を演出します。
[5]気軽に参加できる体験型施策の提供
健康チェックブースや味覚チェックなど、“とりあえず立ち寄ってみた”でも楽しめる体験を用意することで参加のハードルが下がります。
[6] 行動を後押しする参加特典の活用
抽選での景品や参加賞配布など、参加を後押しするちょっとした“ごほうび”も効果的です。デジタルギフトより目に見える景品の方が、職場で目に付きやすく話題になります。
[7] 盛り上がりをつくる発信・演出設計
社内メディアでのカウントダウンや開会宣言、社内報での紹介、経営層からのメッセージなどで“イベント感”を醸成し、参加意欲を高めます。
3.実際の企業事例から見る、健康月間の展開
こうした設計の工夫を取り入れながら、実際に“健康月間”を効果的に展開している企業も増えてきています。ここでは、多様な工夫を凝らして健康月間を設計・実施している企業の事例をご紹介します。
[具体的な先進事例]
ネグロス電工株式会社
従業員一人ひとりが現在の健康状態や生活習慣を見つめ直す期間として、毎年10月を『健康ファースト月間』と定めています。2023年に初めて実施されたこの取り組みでは、“あなたの身体年齢は?”をスローガンに体力測定会などの従業員参加型イベントを開催。また、期間中は社内デジタルサイネージでストレッチ動画や健康情報を積極的に発信し、健康への関心を高め、行動変容を促しています。
東京海上ホールディングス株式会社
社員の健康保持・増進を目的に、10〜11月を「健康増進月間」としてキャンペーンを展開。個人単位の取り組み(MYチャレンジ)だけでなく、組織単位の活動(Ourチャレンジ)、職場ごとのキーパーソンの任命、WEBツールの活用など、多角的に施策を展開。非正規雇用者も参加可能なオンラインイベントも行い、参加率や生活習慣改善効果の向上に取り組んでいます。
日鉄興和不動産株式会社
年に2回、「健康増進月間(1か月間)」を開催。専門講師によるセミナー(ボディメイクやコミュニケーションなど)の実施に加え、社員食堂での健康食品配布や、オンデマンドセミナーの配信など、業務の忙しさに配慮した柔軟な取り組みを展開。全社員がアクセスしやすい仕組みづくりに力を入れています。
トヨタ自動車株式会社
全国労働衛生週間に呼応し、健康づくりイベントを実施。全役員による「健康メッセージ」展開や、職場ごとの健康講演会などを行っています。
株式会社デンソー
身体活動レベルが下がり、飲食機会が増える冬季に「運動習慣づくり」と健康意識を高めるため「健康増進月間」を開催。
― 健康オンラインセミナー(メンタルタフネス向上/姿勢改善セミナー)
― 健康メニューの提供(食堂・売店とコラボ)
― 健康川柳の募集、投票、選考
― ラジオ体操キャンペーン(正しいラジオ体操の動画・資料の配布)
Zホールディングス株式会社
健康増強月間として10月のイベント「UPDATEコンディション月間」ではパラアスリートによるオンラインストレッチ講座やアプリを活用したインセンティブ付与型のウォークラリーを健康保険組合とともに開催。社員の健康保持·増進に努めています。
4.WILLEEの支援
WILLEEでは「健康月間」の設計・運用において、次のようなステップで支援を行っています。
Step1:現状・課題の整理
健康月間を企画するにあたって、まず以下の観点から現状と課題の整理を行います。
- 従業員の健康課題の状況
- 各健康施策に対する従業員の参加状況
- 健康施策の現行想定スケジュール
Step2:設計支援
現状・課題の整理を踏まえて、Why/What/Howの観点を特に重視しながら健康月間の設計を支援します。
[Why] 何のために健康月間を行うか
- 健康月間全体のコンセプト設計
[What] どのような施策を展開するか
- 施策構成の設計(参加型・体験型・目玉施策など含む)
- 各施策の詳細化
- 外部サービス事業者の選定・打ち合わせの同席
[How] どう盛り上げ、関心を高めるか
- インセンティブ設計や発信計画の策定
- ワクワク感を演出する仕掛けの企画
- 経営層、健康経営実務者、安全衛生委員会、労働組合、広報部門などの役割設計
Step3:実行支援
設計した内容をもとに、より多くの従業員に伝わる方法で発信を行い、自然と参加したくなる環境づくりをサポートします。
- プロモーションツールの作成(ポスター、動画、メール文面など)
- 期間中の風土醸成ツールの作成(参加状況等集計、全社展開資料など)
- スケジュールに沿った進行管理
Step4:効果検証支援
一過性で終わらせず、継続的な改善と浸透につなげていくための支援を行います。
- 実績および改善点の整理
- 実施結果の振り返りに関する関係者説明資料・社内広報資料の作成
- 社員の健康意識・行動変容に関するKPIへの影響分析
※参考記事:『健康〇〇の日』45選 啓発期間を掲げて健康施策のWHYを強化する
※参考記事:従業員の主体的な健康づくりを促すPULL型健康施策のススメと施策設計のポイント